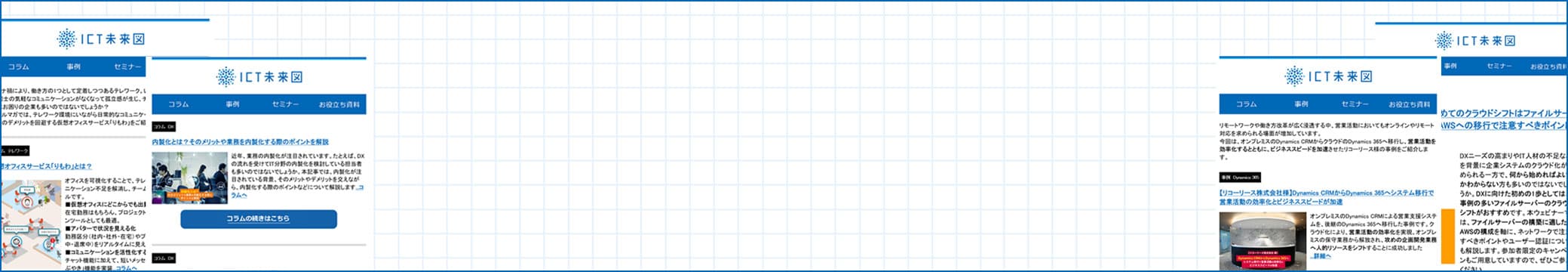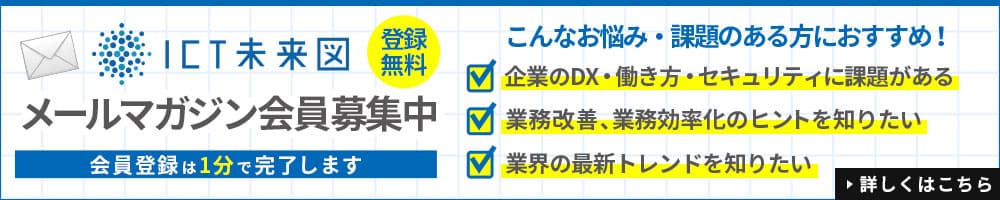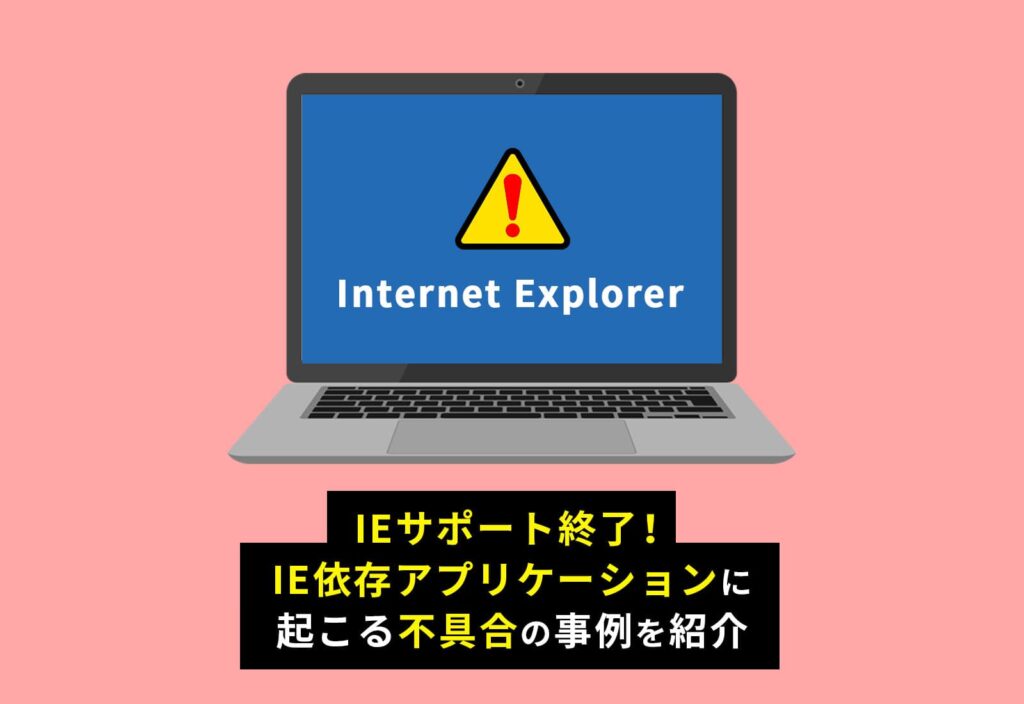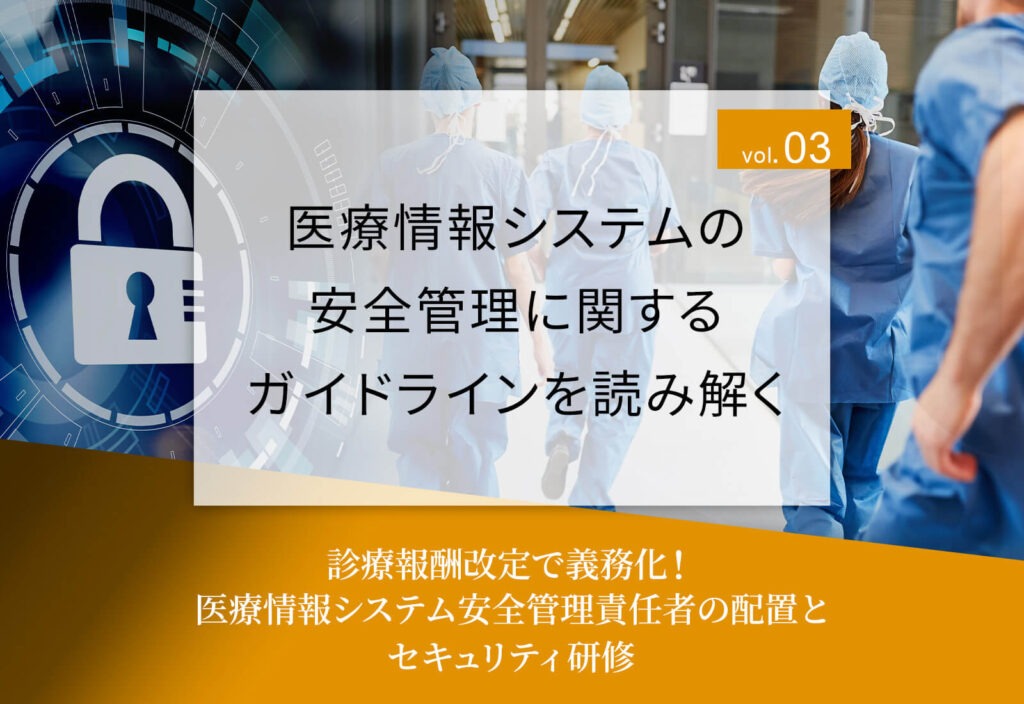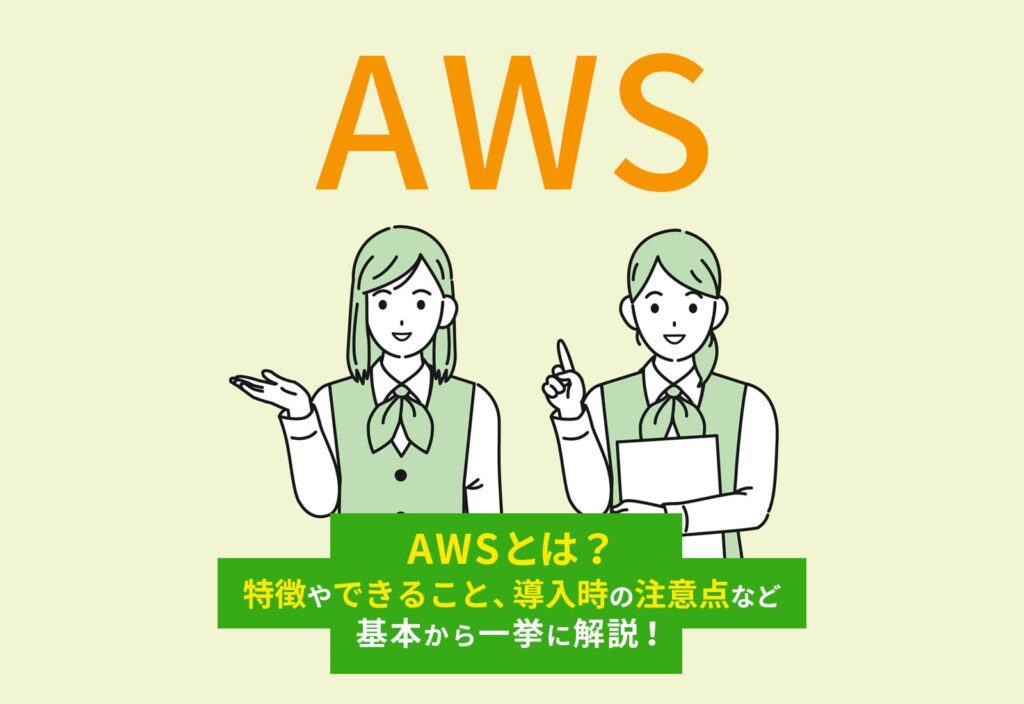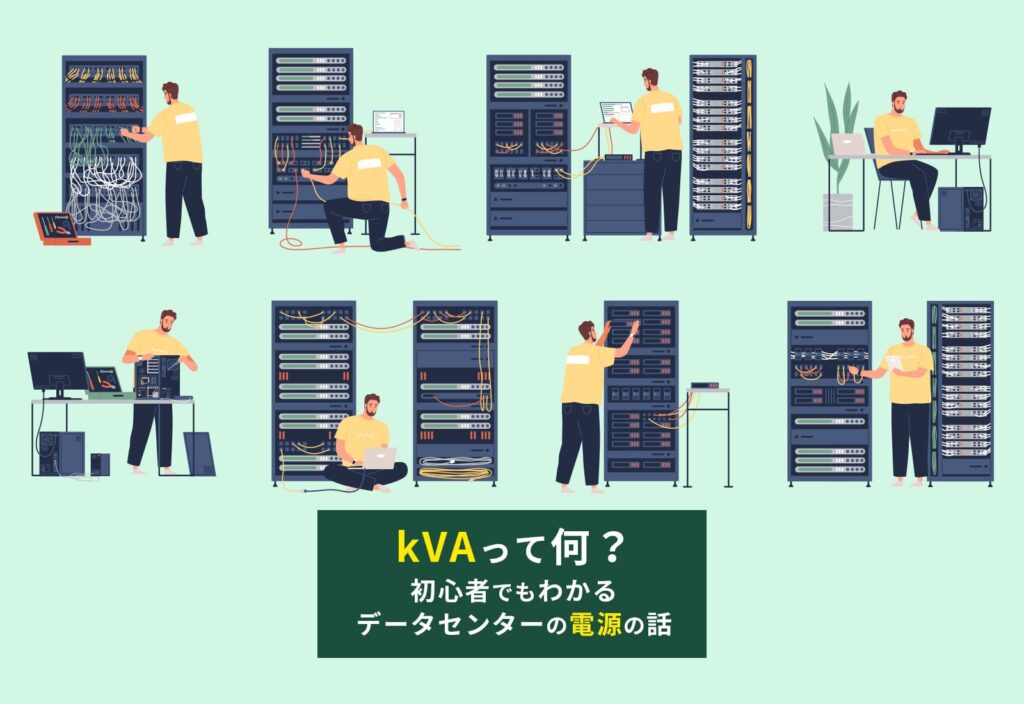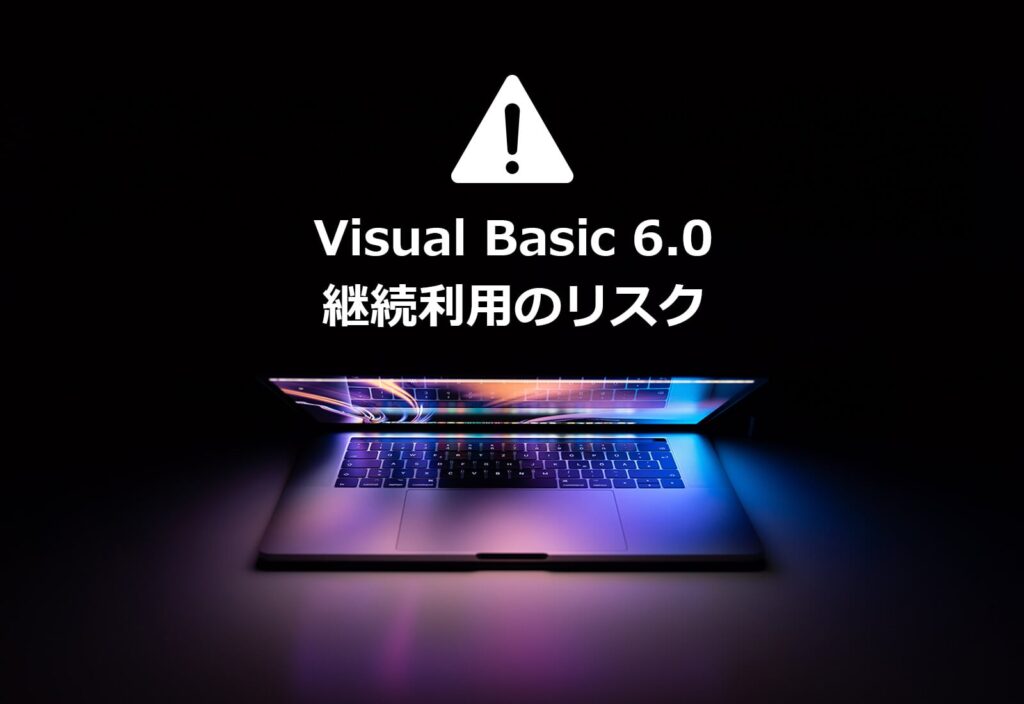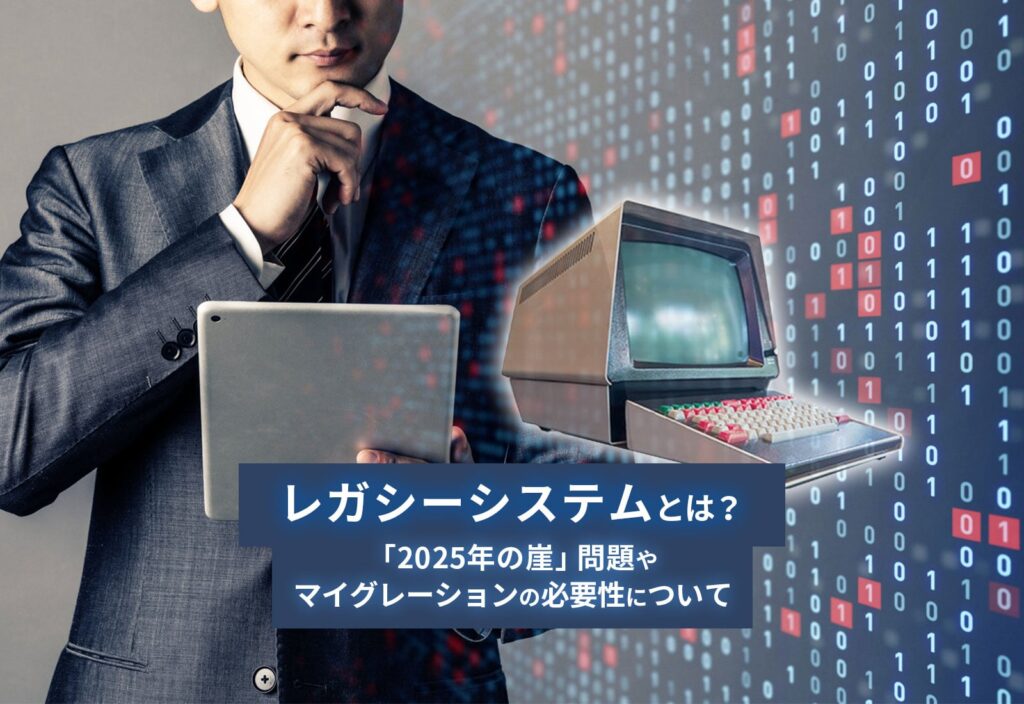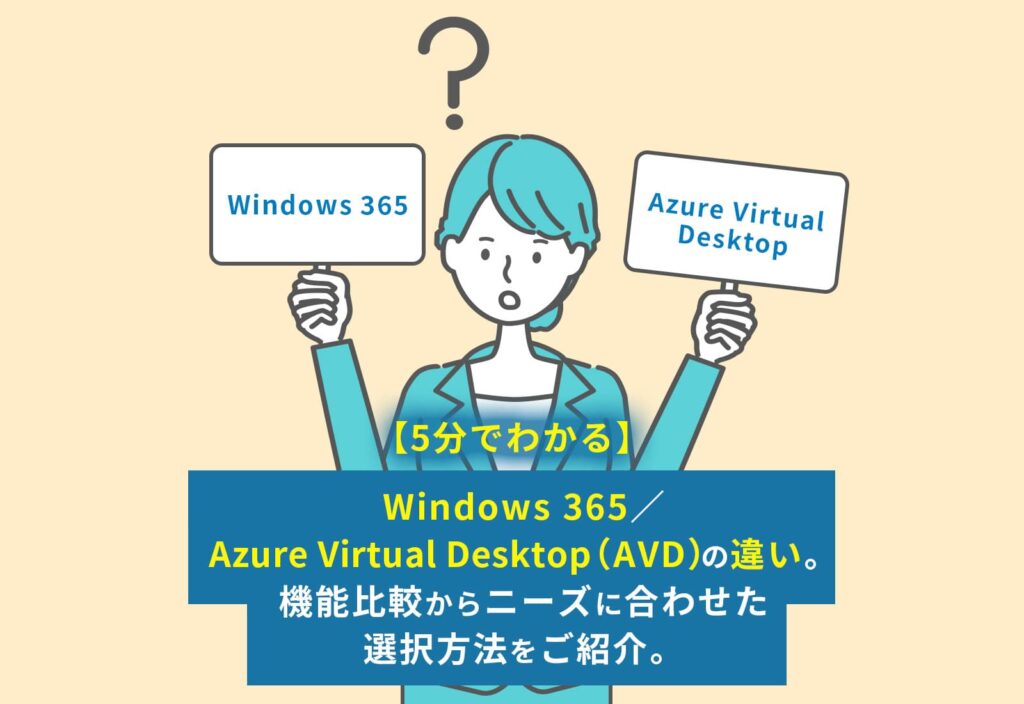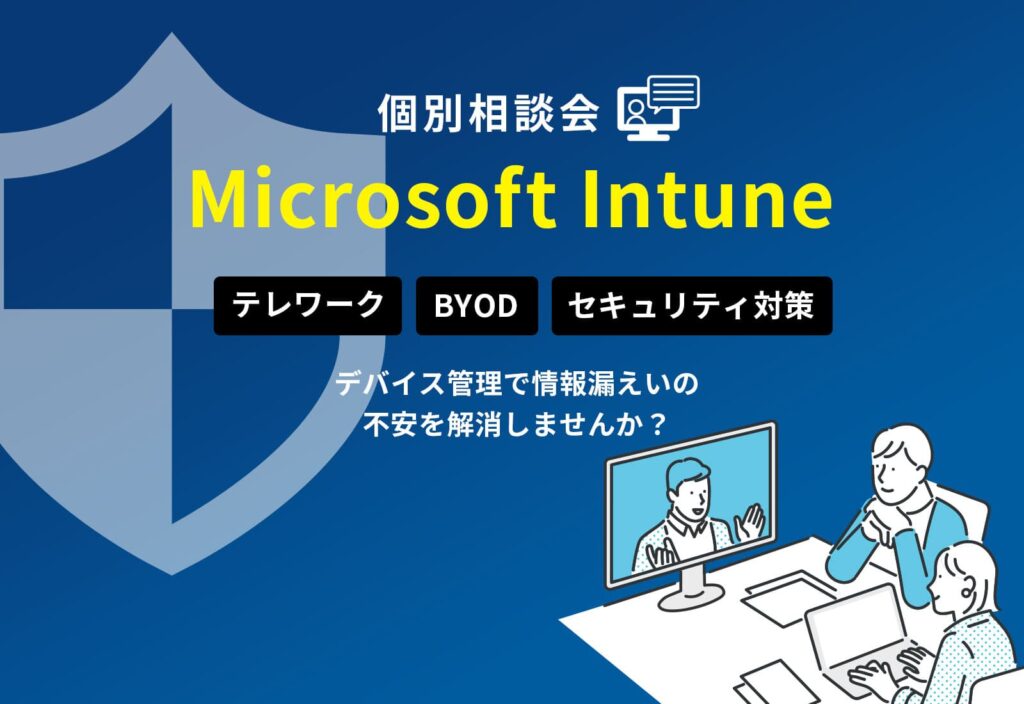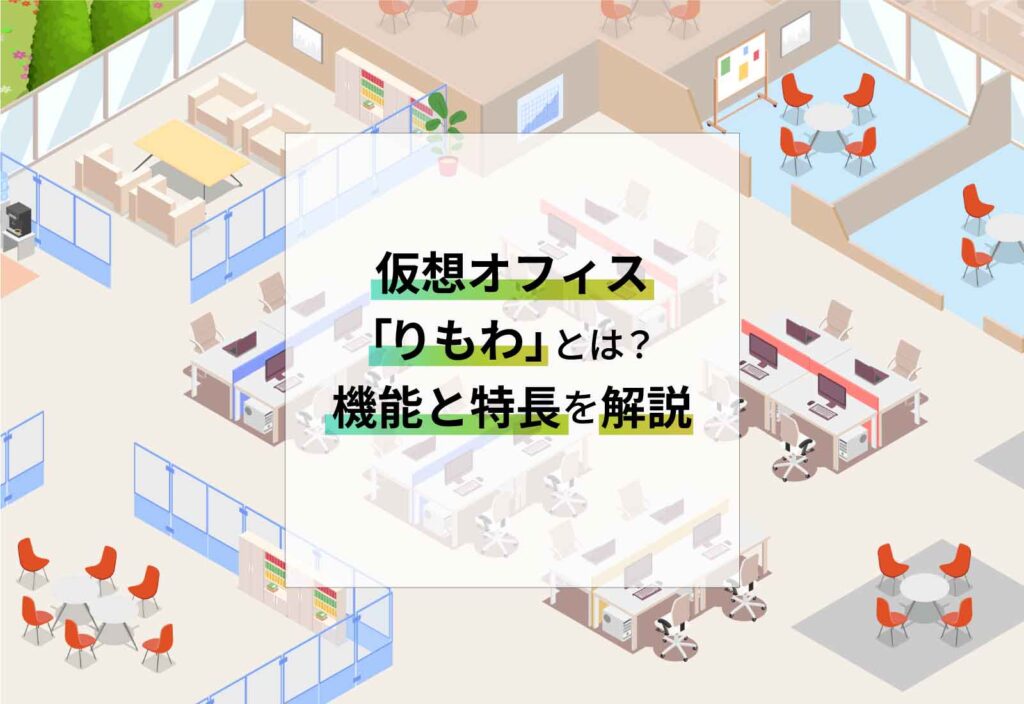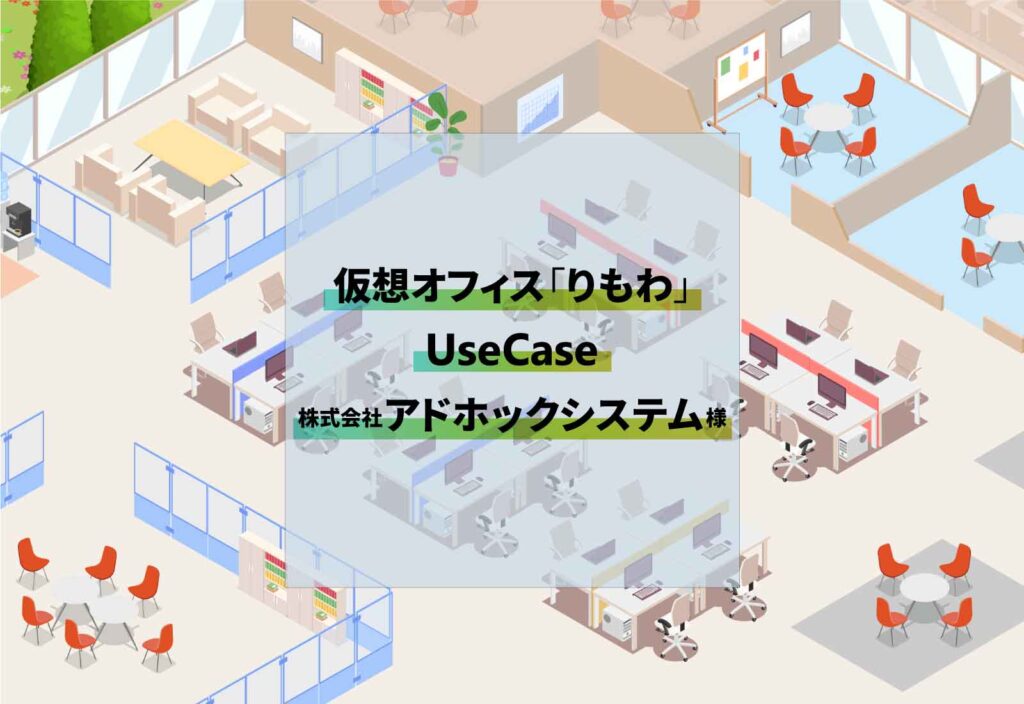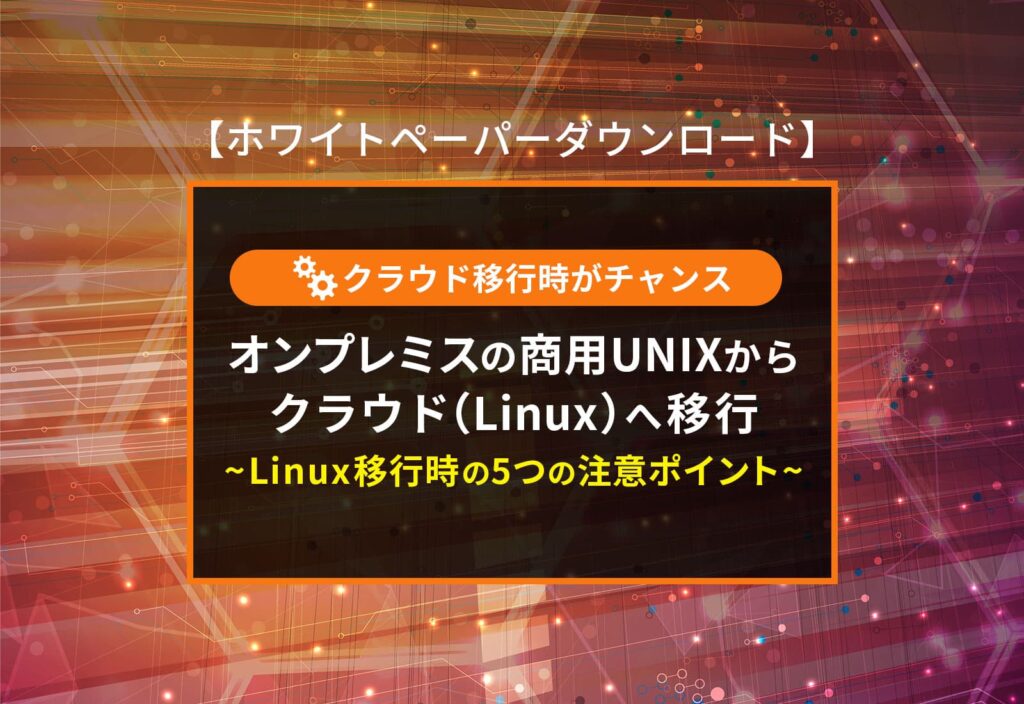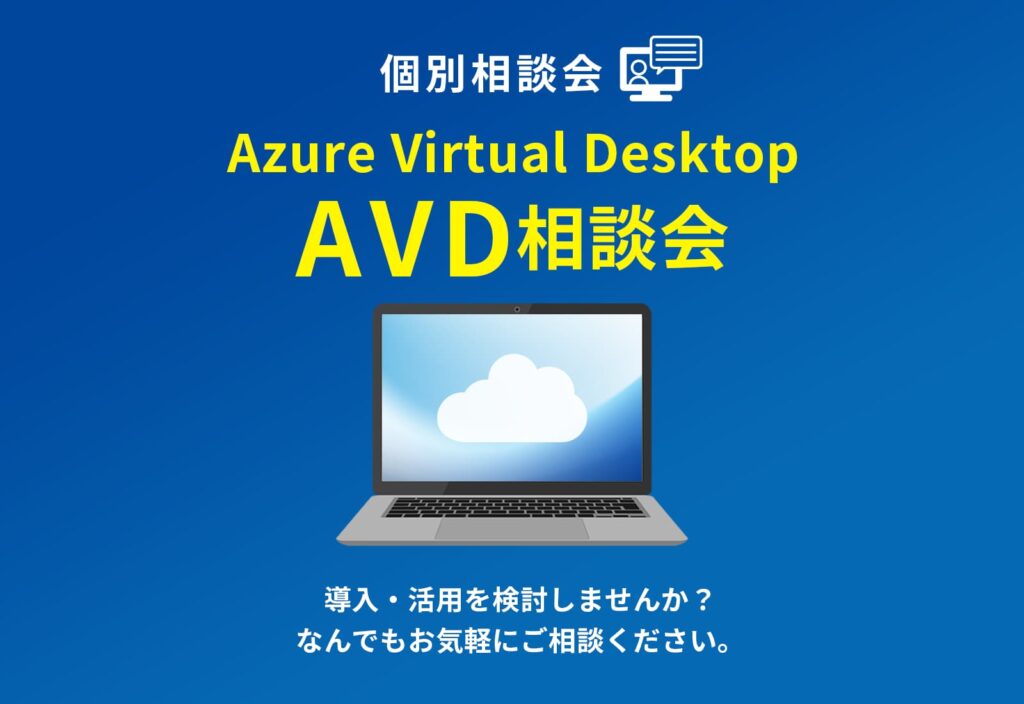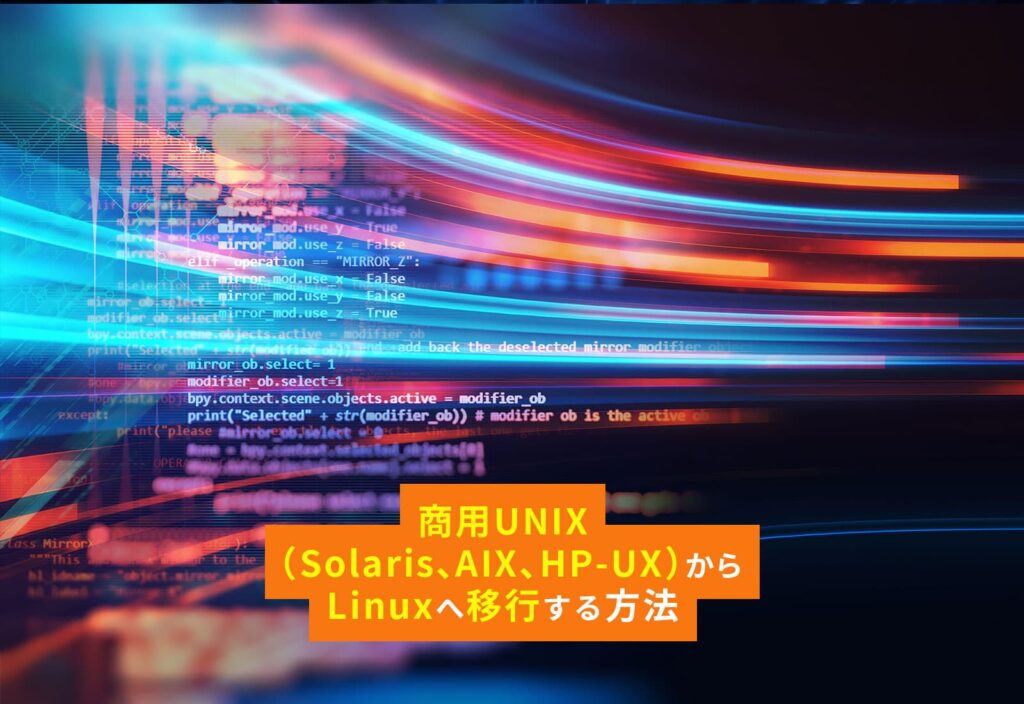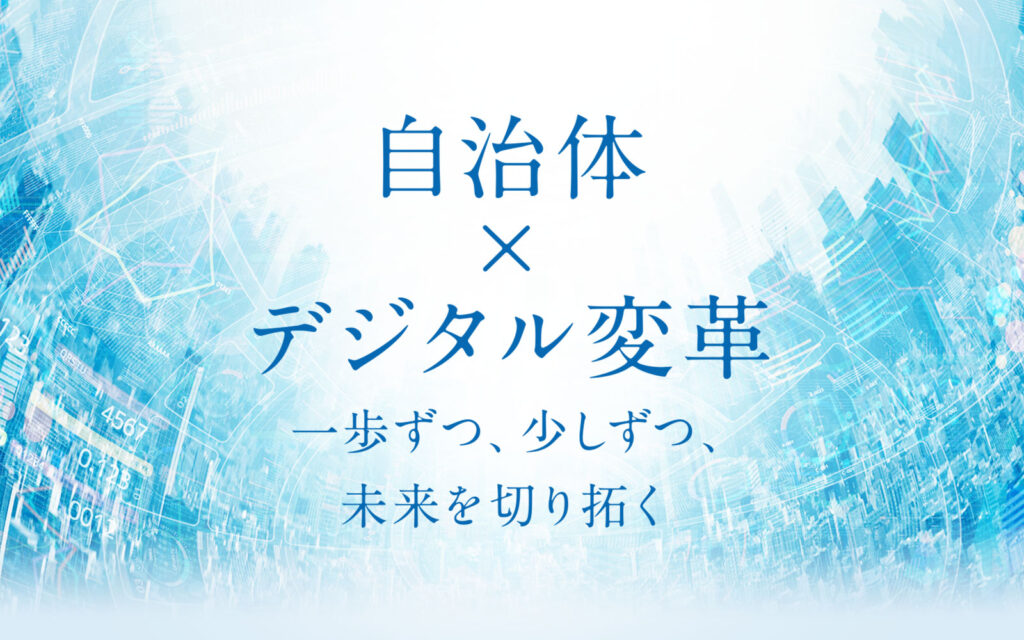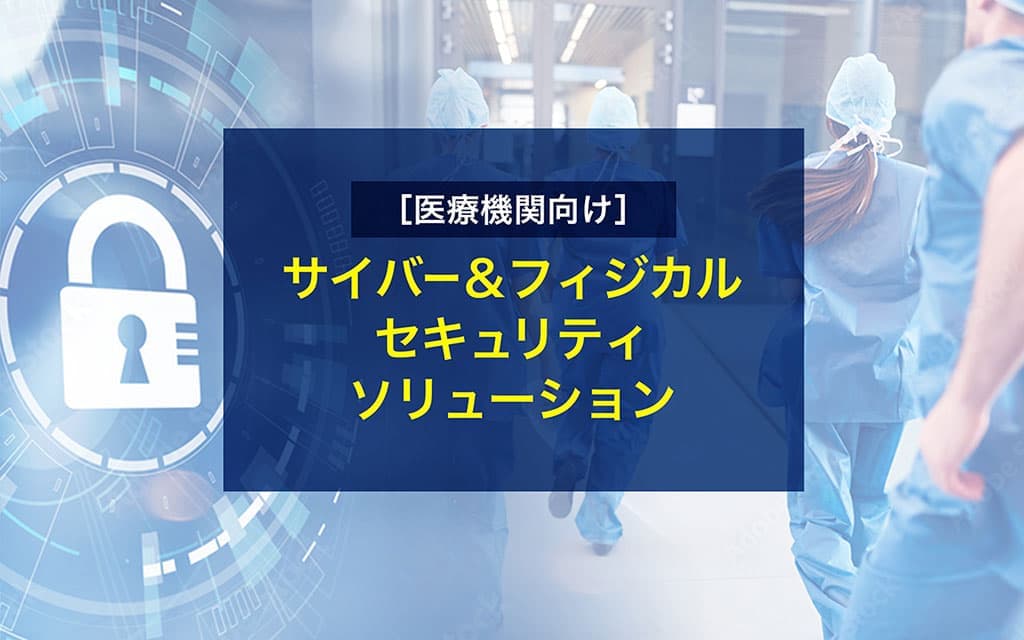-

IEサポート終了!IE依存アプリケーションに起こる不具合の事例を紹介
-



ノーリツ流営業変革でルートセールスの販売実績アップ!-Dynamics 365 ×UPWARDによる地図連携SFA活用事例のご紹介
-



【オンライン視聴】倉庫内業務×トラック入退の連携で業務効率化!倉庫管理システム「LogiPull®WES」で実現する、物流業務の自動化
-


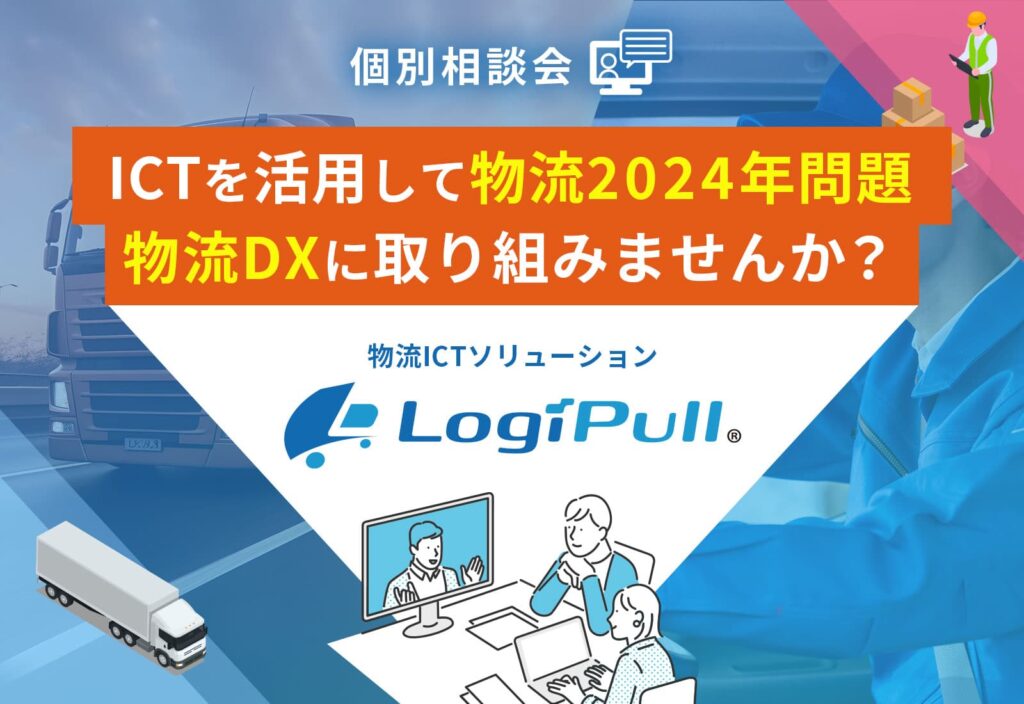
【オンライン相談会】ICTを活用して物流2024年問題、物流DXに取り組みませんか?~物流ICTソリューション「LogiPull®」~
-



【オンライン視聴】成功事例から見る、富士通メインフレームのオープン化 〜短期間・ローリスクで移行可能「リホストマイグレーション」を解説〜
-



【セミナーレポート】5分でよめる「製造業のAWS内製化はどう実現する?〜失敗事例から学ぶ、内製化実現の最適解~」
-


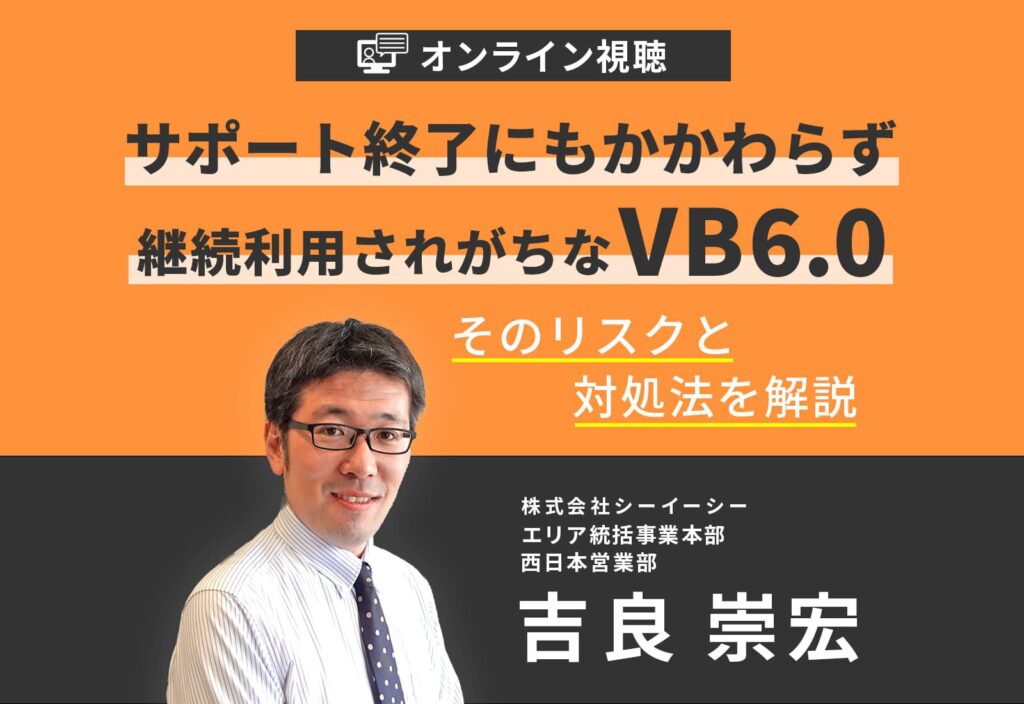
【オンライン視聴】サポート終了にもかかわらず継続利用されがちなVB6.0~そのリスクと対処法を解説~
-


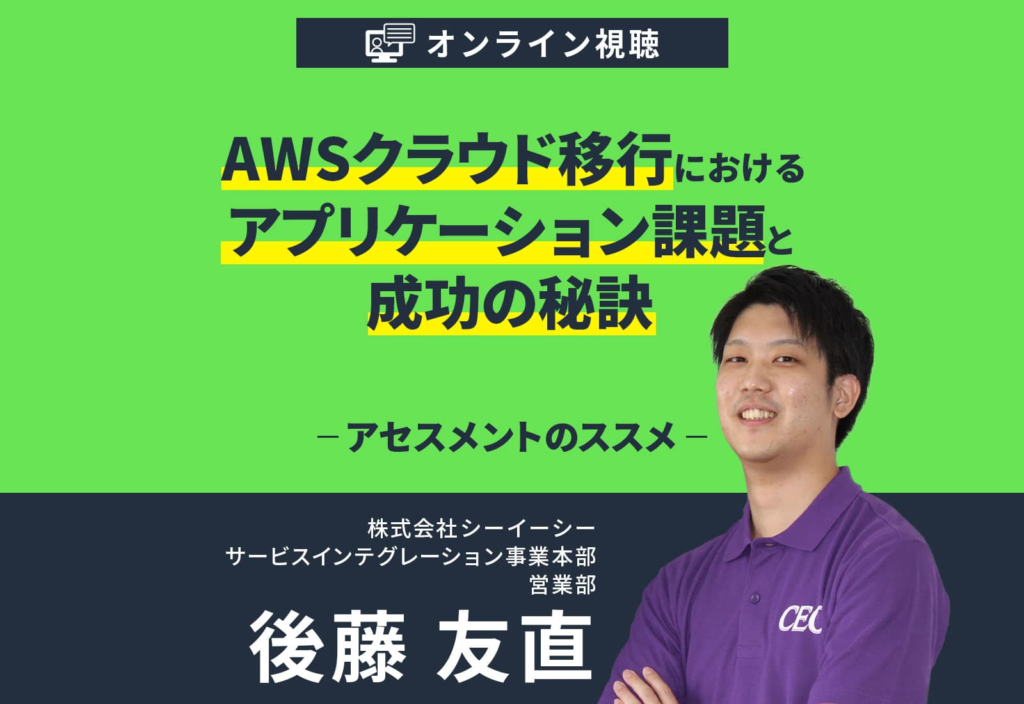
【オンライン視聴】AWSクラウド移行における アプリケーション課題と成功の秘訣 ーアセスメントのススメー
-


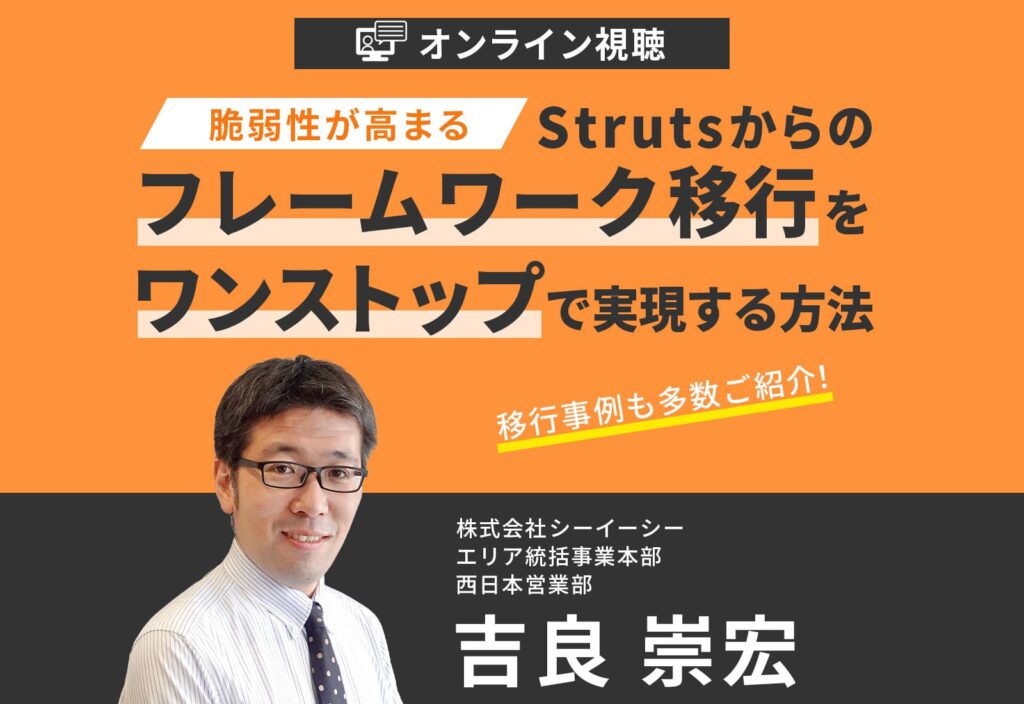
【オンライン視聴】Strutsからのフレームワーク移行をワンストップで実現する方法
話題のICT関連の情報をお届けします。
今すぐ役立つ情報から、少し未来の話まで、ICT技術の「いま」と「先」を見てみましょう。